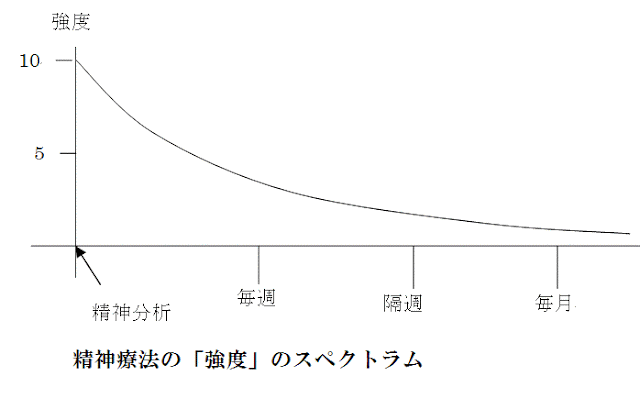怒りの二段階説
ここで怒りが生じるメカニズム、「怒りの二段階説」に関して少し説明したい。怒りというのは、第一段階としてあることが生じ、その反応として第二段階で生じるものである。この第一段階に起きるのが、自己愛トラウマによる心の痛み、というわけだ。
私たちは怒りを本能に根ざした、それ自体が純粋な感情として考える傾向にある。破壊本能、破壊衝動といった言葉は、そのような直接的な怒りの性質を表したものと言える。もちろんそのような怒りもあるかもしれない。しかし多くの場合、怒りは最初に別の感情がわいた後に、つまり二次的に生まれることがわかっている。それがこの「怒りの二段階説」という言葉の意味なのだ。
実はこのような考え方は一般心理学にも見られることを、ここで示したい。最近怒りをどのように理解し、コントロールするかということが話題になっている。いわゆるアンガーマネージメント(怒りの統御))と呼ばれる考え方ないしは手法が臨床の場面で知られている。米国ではうつ病でも薬物依存でも、およそあらゆる治療手段の一環としてこれが登場する。つまり「自分の怒りが生じるプロセスを理解し、それを自らコントロールできるようになりましょう」というのが趣旨だが、その一つの決め手は、怒りを二次的な感情としてとらえるという方針なのである。私がここに示すのは、アンガーマネージメントのレクチャーなどで使われる、「怒りの氷山」の絵(図1)である。このような図はネットなどで非常に多く見ることが出来るが、どれも大体似たような図柄なので、私がそのプロトタイプとなる図を作ってみた(省略)。
この図が表わしているのは、怒りというのはその人の傷つきや恥や、拒絶されたつらさが背後にあり、それに対する反応として生じるのだということである。そしてこのような考え方は精神分析理論とは無関係に、一般心理学的な考え方としてそうだということを表している。ここで水中にある部分の感情をご覧いただきたい。拒絶、恥、プライドの喪失…。いずれも自己愛の傷つきとして理解できるものなのだ。
かつてハインツ・コフートという精神分析家は、従来のフロイトの理論とはかなり異なる考えを打ち出し、様々な議論を巻き起こした。その中で特に注目するべきなのが彼の「自己愛的な憤り」という概念である。つまり自己愛の傷つきによる怒りをこう呼んだわけであるが、それまでフロイトが考えたような、本能としての怒り以外の怒りもあることを彼はこの概念により主張したのである。
私はこの概念に初めて接したとき、コフートは怒りにはいくつかの種類があり、この自己愛憤怒はそのうちの一つを言い表したものに過ぎないと思っていた。ところが日常的に見られる自分やクライエントの怒りを一例一例検討していくうちに、少なくとも大人になってからの私たちが日常生活の中で体験する怒りは、9割以上(まあ、適当な数字だが)がこれではないかと思うようになったのだ。
私たちは日常生活でイライラすることが多い。それこそ電車を待つ列に、急に誰かに横入りされただけでも怒りが生じることがある。そしてその種の怒りでさえも、最終的にはこの自己愛憤怒に行き着くのではないかと考えられるのだ。きっとその時は自分の存在が無視された感じがし、プライドが傷ついたというプロセスが介在していることが多いのである。ただそれはあまりにも一瞬で終わってしまうので、それと気がつかないだけだ。
プライドを傷つけられたときの痛みが急激で鮮烈なものであることはすでに述べた。そしてそれは物心つく前の子どもにはすでに存在し、老境に至るまで、およそあらゆる人間が体験する普遍的な心の痛みだ。人はこれを避けるためにはいかなる苦痛をも厭わないのである。しかしこのプライドの傷つきによる痛みを体験しているという事実を受け入れることはなおさらできない。そうすること自体を自分のプライドが許さないのだ。
かつてコフートという精神分析家は「自己愛的な憤り(narcissistic rage)」という言葉を用いてこの種の怒りについて記載した。最初私はこの種の怒りは、たくさんある怒りのうちの一つに過ぎないと思っていた。ところが日常的に見られる自分やクライエントの怒りを一例一例検討していくうちに、これが当てはまらない方が圧倒的に少ないことを知ったのである。(p.19 l.7~l.10)
私たちは日常生活でイライラすることが多い。それこそ並んで電車を待っていて、急に誰かに横入りされただけでも怒りが生じることがある。そしてその種の怒りでさえも、結局はこの自己愛やプライドの傷つきに行き着くことができる。さらには明白な形で自分の存在が無視されたり、軽視されたりしたと感じられたときには、この感情が必ずと言っていいほど生まれるのだ。たとえレジで横入りした相手が自分の存在に気づいていなかったとしても、また電車で靴を踏んだ人があなたを最初から狙っていたわけではなくても、自分を無の存在に貶められた感じがしたなら、それがすでに深刻な心の痛みを招くのである。(p.19 l.7~l.10)
健全な自己愛と病的な自己愛
ここで自己愛を、健全なものと病的なものとに分けることを試みてみよう。もちろん健全な病的な自己愛とを明確に分けることなど出来ない。あくまでもどれだけ健全な(あるいは病的な)部分を持っているかという話である。そしてその際判断基準となるのが、これまでに述べた怒りがどの程度強く、それがどの程度コントロール不能となる可能性があるかということだ。
健全な自己愛を持つ人は、自分が保つべきプライドがあり、それが傷つけられそうになった時には反撃が出来る人であろう。ただし人には守るべき分があり、プライドもそれに沿ったものとなる必要がある。自分と同じ立場の友達には意見の立場を明確に表現しても、年長者や目上の人に対しても同じような態度をとるわけにはいかない。だから健全な自己愛の表現は、自分が社会におかれた立場を鑑みたものになる。
ところが自己愛はある条件下ではどんどん肥大する可能性がある。それは自分にアドバイスをしてくれたりいさめてくれたりする存在が周囲にいなくなる場合である。すると自分の意に沿わない人がいるとそれに腹が立ち、攻撃してしまうようになる。
そのような様子を描いたのが次の図である(省略)。
この図の中心部分にある濃いブルーの部分が健全な自己愛を描いているものと思っていただきたい。ここは言わば心のパーソナルスペースとも呼べるものである。パーソナルスペースとは私たちの身体の周囲の一定の空間であり、そこに他人が侵入してくることを不快に感じる部分である。ただしもちろん親密な人との接触や挨拶の際の身体接触は除く。誰だって新幹線の自分の席の前のスペースにとなりの人が足を伸ばしてきたら不快であろうし、足を引っ込めてくれるように要求するのは当然である。となりの人の肘が肘掛を越えてこちらに侵入したとしても同じだ。そしてもちろんあなたもとなりの人のパーソナルスペースを尊重するだろう。それと同じように、社会の中で自分が自らの分に従った振る舞いをし、正当に与えられた自らの権利を行使することは健全なことである。
ところがこの心のパーソナルスペースは、甘やかされると肥大していく。自分が限りない権力を持つと信じて周囲にそれに屈服することを要求する。自己愛の風船は膨らみ、ちょっとした刺激により爆発する可能性が出てくるのだ。