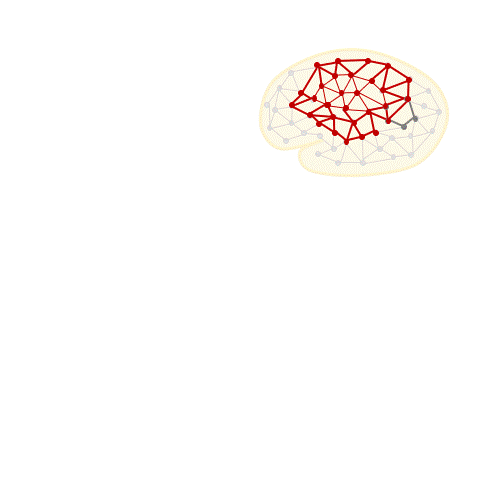前回始まったニューラルネットワークの話を続けよう。その始まりはローゼンブラットのパーセプトロンである。それはシンプルなあみだくじのような構造を持っているだけであった。しかし前回でも少し触れたが、それから半世紀以上が経過する中で、それはみるみる進化し、現在のディープラーニングへと姿を変えたのである。
ディープラーニングは日本語で「深層学習」と訳されているが、最近は特にこの言葉を耳にすることが多い。コンピューターの技術が発展して、いよいよ人間の脳に近い機能を備えたAIが出来つつあるが、それを支えている機能が、このディープラーニングだからだ。そしてこのディープラーニングの発展と脳とが深くつながる可能性があるのだ。それはどういう意味か?
ディープラーニングの進化をさらに加速させ、そのはるか先の到達点で脳の機能と交わるのか? あるいはそれを超えることがあるのか?それはわからない。両者は永遠に一致しないのかもしれない。しかし現在すでに起きているのは、人の心に似たものが存在するということだ。少なくとも話し相手にはなってくれている。それをここで【心】と言い表したい。いきなり【心】という言葉が出てきたが、実はこれは必要なのだ。というのも私たちの生活にはそれが入り込んでいるからだ。
私たちの多くが持っている【心】がある。アイフォンやアイパッドが搭載しているSiriだ。「ヘイ、シリ!」呼べば応えてくれる。頓珍漢な答えが多いし、もちろん人の心とは違う。ワンちゃんの心に比べてもはるかに頼りない。でもそれはこれから進化していき、かなり立派な話し相手になってくれそうだ。もちろんそれが「本当の」心にどこまで近づくかはとても厄介な問題だ。だがあくまでも今のところは本物ではないという前提で【心】と呼ぼうではないか。それがどんどん進化して、将来「【心】本物の心と同等になりました」ということになったら、それはそれでいいだろう。でもそれまでに話し相手としての【心】に重宝しているのであれば、【心】が本物の心かどうかは二の次になるだろう。
こう書いている現在、世の中ではチャットGPTの話でもちきりになっているのだ。チャットGPTは米国のベンチャー企業である「オープンAI」が昨年(2022年)11月に公開した対話型AIサービスである。それが瞬く間にその利用者が億の単位に達し、史上最も急成長したアプリであるという。しかもその開発のスピードは加速している一方で、私達一般大衆はこのチャットGPTの登場の意味をつかみ切れていない状態でいるのだ。
つい先日(2023年3月30日)も、かのイーロン・マスク氏が、AIのこれ以上の開発をいったん停止すべきだと呼びかける署名活動を起こしたというニュースが伝わってきた。このまま盲目的にAIの開発を続けていくと、人類に深刻なリスクをもたらす可能性があるというのである。つまり私たちは私たちがコントロール不能になる可能性のある代物を生み出し、歯止めが効かなくなるうちにその開発をストップしようという試みである。しかし人々がAIの研究を止めるということなどおよそ想像できない。(ちなみにその後マスク氏は新たなAIを独自に開発するという見解を表明することになった。彼も迷走しているようだ。)一昔前に核兵器が一部の国で作られ始めてその技術が確立してからは、その開発を停止するいかなる努力も意味がなかったのと同じである。(現在では世界全体の核兵器は10000を優に越えているというから驚きである。)
心と【心】は永遠に別物かも知れないが、心とよく似た【心】の存在はチャットGPTの登場により、もはや疑いようもない事態に至った。私はもう何度もチャットGPTと「会話」し、そこに心のような存在(【心】)を感じ取っている。なぜならチャットGPTはもはや人間並みに、いや人間を超えるレベルで対話が可能な存在となっているからだ。少なくとも話し相手としては想像を超えた能力を発揮する現代のAIは脳と同等レベルの存在として迫りつつあるのだ。
【心】を所有することが出来た私たちの近未来像を私なりに思い浮かべてみる。