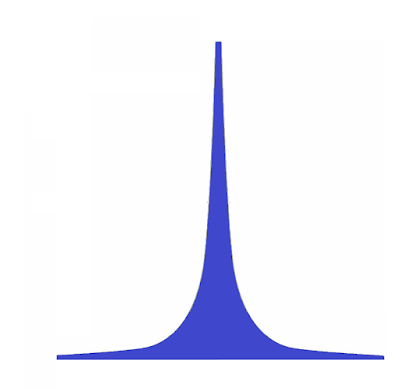これまで主として物質に見られる揺らぎについて述べてきたが、揺らぎの問題は結局はランダム性や予測不可能性に通じているということを、ある程度はお伝えできたのではないか? そう、世界が揺らぎで構成されるということは、世界での出来事は、そして人の心は基本的には予測不可能な「ランダムウォークrandom walk」であることを意味するのである。
ランダムウォークと予想不可能性
ランダムウォークは今では「ランダムウォーク理論」として確立しているが、もともと酔っ払いの千鳥足のことである。「酔歩」という訳語もあるくらいだ。つまりどこに向かうかが全く偶然に、アットランダムに決まる場合、その人はどこに行くのか。おそらく私たちの多くがイメージするのは、「結局その場を足踏みするのではないか、あるいはその周囲をうろうろするだけでどこにもいかないのではないのか?」ということである。
このことを少し数学的に表してみよう。ある酔っ払いの代わりにコイン投げを考える。何度もコイン投げをして表が出たら一点をプラスし、裏が出たら一点マイナスとする。そして一回ごとに変わる点数を縦軸に、横軸にはコイン投げの回数を取ってみる。
皆さんに変わって私がそれを描いてみた。大体こんな感じになるのではないか。表と裏が出る確率が半々だとすれば、その累積点数は結局ゼロの周辺をうろうろするであろう。現実がこのように動いてくれるならば、大体このコイン投げのゲームの結末は予想がつくということになろう。勿論少しのプラス、マイナスはあるだろうが、それも誤差範囲ということだ。
ところが実際の例では以下のようになる。といっても10人の人を集めてコインゲームをしてもらったわけではない。コンピューターを用いて乱数をもとに仮想上のコイン投げを一万回してもらったわけである。するとその結果は以下のとおりである。
この図からわかることは、コイン投げを一万回試行してもらっても、その結果はこれだけバラけてしまうということだ。それぞれの点数が揺らぎを持った曲線を描き、ゼロに収束するどころか離れて行っているようである。ことから皆さんが気が付くことは、ランダムウォークは偶発性に基づきながら、一見何らかの規則性を有しているという印象を与えるということだ。もしこれがチンチロリンを複数の人がやった時の成績だとしたら、一番上の黄土色の人は明らかにその名手であり、他の数人よりぬきんでて得点を稼ぎ、それでも成績の上下は伴っているということになる。そしてこの得点の総計の上下のラインは、まさに揺らぎを有しているのだ。そしてこの思考の最初には、誰も自分がどのような点を獲得するかは一切わかっていなかったということである。なぜならこれはすべてコンピューターが作り上げたものだからである。しかしそれでも私たちはこの揺らぎの向かう方向に何らかの法則や規則性、原因を見出さないわけにはいかない。
世界が揺らぎにみちているということは、この世界の出来事には実は原因や規則がないものが多く、その意味でランダム性に支配されており、将来を予想できないという事である。このことに人類は徐々に気が付いてきたわけであるが、最近になり、揺らぎという考えかたへの注目と共に、それが明らかになりつつあるというわけだ。そしてそれ以前は、人類はみなことごとく運命論者であったと言えるだろう。「未来は決まっている。ただ人間はそれを知らないだけで、全知全能の神ならそれを知っている」と考えたわけだ。そして精神の高みに至った人のみがその未来を予言する力を得るとも考えられていた。あるいは科学の発展によりそれをより正確に予想できると考えた人もいただろう。
しかしその科学がある程度進んだ段階で、私たちは世界が不確定性に支配されていることを知るに至った。あらゆる出来事の根底にランダム性があり、未来は原理的に予想不可能なのである。たとえば半年後の今日、空が曇っているか快晴かは全くといっていいほど予測が付かない。チンチロリン(どんぶりとサイコロを用いた一種の賭けごと)で小銭を儲けようとしても、一回振るごとに次はサイコロのどの目が出るかはわからない。あるいは今日の夕方東京発6時50分の新大阪行きの新幹線が、途中で事故もなく目的地に定刻に着けるかは、実際に乗車してみないとわからない。ましてや今世界じゅうがコロナウイルスに震撼するような事態を、一年前にはだれも予測していなかったのである。